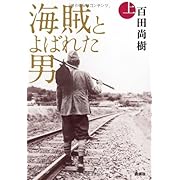
社員は家族である
明治の終わりに創業後、満州にまで業態を拡大し続けた同社が昭和15年までの約30年間個人事業主であったことは本書を読んで初めて知りました。それも銀行からの借入や対外的なイメージの上でといった理由のようで、株式会社への法人成りは出光氏の本意ではなかったようです。
出光氏の最大の理念は「社員は家族である」ということだと思います。ドキュメンタリーではないので真意のわかるところではないのですが、戦後海外から復員してきた従業員の馘首をせず、見舞金まで出していたとのこと。ほぼ石油専業でやってきた同社にとり、また原油の採掘がほぼなく輸入一辺倒であったこの業界は、GHQで完全統制がとられた戦後の時期は需要はあれどない袖は振れないの状況で決定的なダメージを負わされたことは想像に難しくありません。加えて戦中の石油規制にことごとく反発し続けた同社は、戦前より市場を国内から海外へ振り向けており、戦後海外での営業が行えなくなったことは同業他社と比較し完全にマーケットを閉められた状況であったといってよいでしょう。
そのような経済状況下においても従業員を切り捨てず、旧海軍通信兵だった者からGHQの意向によりラジオの修理を手がけるなど、本業以外に売上の開拓を行い従業員の維持に奔走していたようです。
 戦中と戦後の「国のため」の維持
戦中と戦後の「国のため」の維持
天皇が「人間」となり、戦中と戦後の「国のため」の意識は180度転換させられたわけです。多くの日本人が意識を集中させてきた(させられていた)「国のため」が何なのかわからなくなって廃人同様になった人も多くいると聞きます。富国列強を是としていた日本への「国のため」と、GHQによる統制と敗戦復興をしなくてはいけない日本への「国のため」は、目指すものが違うような気がします。歴史を知らない人間の勘違いかもしれませんが、昨日まで違うといわれていたものが今日からは正しくなるというときに、それを受け入れることができたのはなぜなのか。
人間の欲による「国のため」ではない、民族としての「日本人のため」と言い換えることができるものなのか。当時を知らない人間は想像することしかできないのですが、その違いを知りたいと思います。
私たちサラリーマンは辞令一つでどこへでも行かなくてはなりませんし、誰とでもつき合わなくてはいけません。昨日まではこうだと言っていた上司が、代わったとたんにそうではないと言われれば従わなくてはなりません。話のレベルは違うのは承知の上ですが、どこか私たちもその方向転換について、学ぶことができることがありそうです。
2013年本屋大賞1位の作品
戦後日本初の世界最大タンカーを建造したことは有名で、NHKのプロジェクトXでも放送されたことがあります。同社は2006年(平成18年)まで未上場で、ブリジストン、サントリーと同様に創業者(家)の影響力が相当強いんだろうなという印象を持っていました。「社員は家族である」がパブリック企業としての上場企業を否定するものではないと思いますが、そのような一面が、長く非上場企業であった理由なのかもしれません。
0 件のコメント:
コメントを投稿